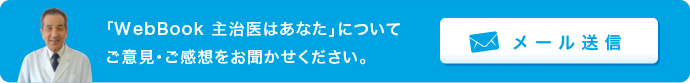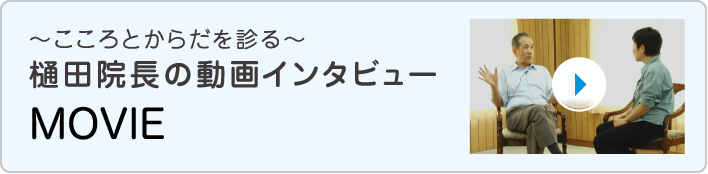現代の医療のあり方に一石を投じ、これからの医療の可能性を模索する。
心身統合医療に力を注ぐ、医師・樋田和彦のメッセージ。
本来の診察とは、
患者さんの身体・心・生活に触れること。
■ときには過去の体験までさかのぼって診ることも大切
私が医師として医局に入ったとき、当時の教授からこう言われました。
患者さんが診察室に入った瞬間から、わずかな時間も観察を怠ってはならない。そして診察時には、大方の診断ができていなくてはならない」。
すばらしい言葉だと思いませんか。医者としてのセンサーをフルに発揮して、目の前にある「生きた情報」を自分なりにインプットしなさい。そう言っているのです。当時は、医師が患者を診るという技(アート)が残っていたんですね。ところが今はどうでしょう。電子カルテの操作に忙しく、パソコンの画面ばかりに気を取られながら診察している医者もいるようです。教授の受け売りではありませんが、診療は診察から始まると言っていいと私は思っています。
生きた情報には、診察の基本である次の4つが含まれます。
- 視診
- 触診
- 聴診
- 問診

これらの診察から得られる情報を通じて、患者さん自身をしっかり診るということです。その人自身を診るということは、単に身体の症状だけでなく、本人を取り囲む環境や周囲との関係性、場合によっては過去の体験までさかのぼって全体的に診るということだと私は考えています。どういうことか、私の診察を例にとってご説明しましょう。
例えば、日常的に、難聴・耳閉感・めまい・耳鳴を訴える患者さんに対しては、次のような順序で話を伺うようにしています。
- 患者さんの訴えをよく聞きます。
何時ごろから? どのように? 程度は? 頻度は? - 発症した頃、事柄・出会い(人間関係)・自分の役割にストレスを感じたことはなかったか?
- 過去に同じようなことは起こらなかったか?
- 耳の症状以外に、全身の健康状態はどうか?
- 家族に耳の病気を持った人はいないか?
このように、既往歴、家族歴も含めて、じっくりと話を聞いていくのが私の診療方法です。つまり、患者さんの身体・心・生活に触れることを何よりも重視しています。家族関係や職場での人間関係がうまくいかず、「聞きたくない、聞きたくない」と耳をふさいで生活している人は難聴になりやすいように、症状だけでなく、生活にまで踏み込んだ問診が必要の場合が少なくないのです。
私が行っているような診察は、以前は当たり前のようにされていました。しかし最近は、診察の基本とされた「視診」「触診」「聴診」「問診」は2の次、3の次となり、患者さんが嫌がるからといって、聴診器すら当てないケースもあると聞きます。
■医師と患者の関係性を、もう一度、基本に戻すべき
こうした変化の要因のひとつとして考えられるのが、医療機器の発達です。
「胃が悪い」と患者さんが訴えれば、その病名を明らかにするために、まずは患部を中心としたレントゲン検査や胃透視、CTあるいは胃カメラといったデータ収集が第一となります。医者は、撮影された患部の画像ばかりを見つめ、そこに表れるデータで診断を下そうとします。もし患者さんが、「原因は何でしょう?」と尋ねたとしても、医者は「食べ過ぎじゃないですか?」と答えるぐらいにとどまり、胃にトラブルを抱えるまでに至った、患者さんを取り巻く環境や状況は確認しようともせず、いきなり治療が実行されてしまいます。
より医学を進歩させるために登場した医療機器ですが、その発達によって、医者と患者との間には、ずいぶん隔たりが生まれているように感じます。温かい、人間と人間の関係性が薄れてしまったように思えてならないのです。もちろん、正確なデータを得ることは非常に大切なことです。しかし、目の前の患者さんが発するサインを注意深く見ようとせず、コンピュータの画面ばかり眺めていたのでは、本当の医療はできないのではないでしょうか。
診察室で向き合う、医師と患者さんの関係性を、もう一度、基本に戻すべきだと私は思うのです。ただし、皮肉なことに、私が大切にしている診察方法ですと、保険診療の枠に当てはまらないことが多い。開業当時は、全て自分で点数計算していたので、診察している時点で、患者さんが窓口で払う金額が嫌でも分かってしまう。すると、診察中でも点数が気になってしまうわけです。
「このままではダメだ」と危機感を覚え、特殊外来診療という枠を設けました。もう点数はどうでもいい、そう思えるようになった時点から、ようやく医療の醍醐味や奥深さが分かるようになった気がします。
私の好きな言葉に、こういう一節があります。
「百年以上も前、身体の領域は医者に、心の領域は心理学者に、魂の領域は教会に委ねられた。しかし、このような境界は、もともと存在しない。私たち人間が勝手につくり上げた境界なのだ」。
グラディス・テイラー・マクギャレイ著「内なるドクター」より
次回は、医者という生業(なりわい)についてお話します。