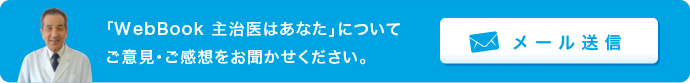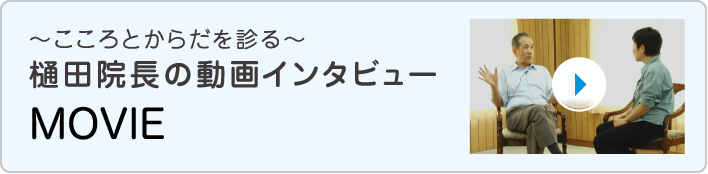現代の医療のあり方に一石を投じ、これからの医療の可能性を模索する。
心身統合医療に力を注ぐ、医師・樋田和彦のメッセージ。
患者数や手術件数にこだわるより
医者の本分を尽くしたいと思います。
■鼓膜切開の件数にこだわる風潮に違和感を覚えた日々
子供の頃、神経質で病身だった私がよく通った近所の鍼医者さんは、スマートで優しい印象の方でした。身体のどこが悪くても、いつも同じ手順でハリを打ち、マッサージをしてくださり、丁寧に1時間近くかけて診てくれたものです。のんびりしたものですが、家庭医として心温まる医療でした。
ところが、慣れ親しんだ医療とは裏腹に、43年前に私が開業した耳鼻科診療は意に反して対極へと向かっていきました。最初の3か月で患者数は100名を超え、その後も増加の一途をたどったことが原因でした。経営の面から見れば、患者数は多いほうが良いに決まっていますが、いつの間にか3分診療の習慣が身についてしまい、患者さんから「症状の改善が遅い」といわれても、きちんと返答できないまま「もう少し様子を見ましょう」と繰り返すような有り様でした。
そんな状況が2年、3年と続くうちに体調を崩し、気が滅入って動悸、不整脈、めまいに苦しむようになりました。その頃のことは、chapter2に書かれているので詳しくは割愛しますが、耳鼻科診療を生涯続けることに不信と不安を感じたものでした。さらに私の不安をかきたてたのが、鼓膜切開の件数にこだわる当時の耳鼻科の風潮でした。学会のリーダー的立場の方が積極的に鼓膜切開を勧めたことによって、鼓膜切開の件数が多いことが学会で評価されたりして、どうしても違和感を覚えずにいられなかったのです。
私は手術が苦手というわけではありません。勤務医時代は他院のヘルプとして、数多くの手術をお手伝いしましたし、それなりの経験も積んでいました。しかし、鼓膜切開は必ずしも無痛ではなく、子供の体を抑制する(抑えつける)ような無慈悲な扱いや家族の不安など、ネガティブな面が強くあったために、積極的になれなかったのです。もちろん切開のメリットは承知していましたが、切開をすることで再発しやすいケースがあるのも気になりました。やがて私は、特に子供たちに苦しみを与える診療に対して、強い罪悪感を持つようになっていったのです。
今は、めったに切開はしません。そのかわり、本人と家族、特に母親の不安を取り除くように努めています。診療についても、できるだけ優しく温かいポジティブな雰囲気づくりを心がけています。ときには「小児鍼」といって、頭や耳や手足にハリを刺すのではなく、ハリの先で皮膚をこすることでリラックスをもたらす医術も必要に応じて使います。
■ネガティブなものを排除できれば、病気はスムーズに経過する
なぜ、私がこうした診療に至ったのか。過去を振り返りつつ考えてみますと、早くからトラウマに関心を向けてきたからだと思います。
ある時、60歳ほどの女性が耳痛の訴えで来院されました。まず気づいたのは、緊張の度合いが尋常ではないこと。その方は、身体を震わせて診察台に座りました。問診などを済ませ、耳に触れようとしたとき、急に立ち上がり「耳には触らないでください!」と大声で叫んだのです。
驚いて事情を尋ねますと、本人に記憶はないが、母親の話によれば、1歳半のとき中耳炎で鼓膜切開を受けたことで恐怖心が身につき、病院へ行けなくなったというのです。1歳半といえば思い出せる年齢ではありません。幼いときほど心身ともに深くネガティブなエネルギーが記憶されるようです。
この方の場合、かなりの時間をかけてトラウマ療法を続けるうち、恐怖心から抜け出すことができました。このような症例を度々経験するうち、安易に鼓膜切開はするものではないと深く心に刻むようになったのです。
身体には自然に治ろうとする本能があり、化膿もまた治ろうとする本能的な現象です。化膿そのものは、病状経過のひとつで、身体にとっては善であり必然性のもの。見方によっては、化膿まで至らなければならないほどの負荷があってのこと、ともいえます。医療の役目は、スムーズに病気を経過させることにありますが、経過の妨げが、化膿まで追い込むこともあるのです。その妨げが不安や不信や恐怖にあると思っています。こういったネガティブなものを排除できれば、病気はスムーズに経過し、外科的な処置を少なくすることができると考えています。
「現代の医師は情報に埋没し、技術に圧倒されている」。
デレク・ボク (ハーバード大学総長)
次回は、医学と医療についてお話します。